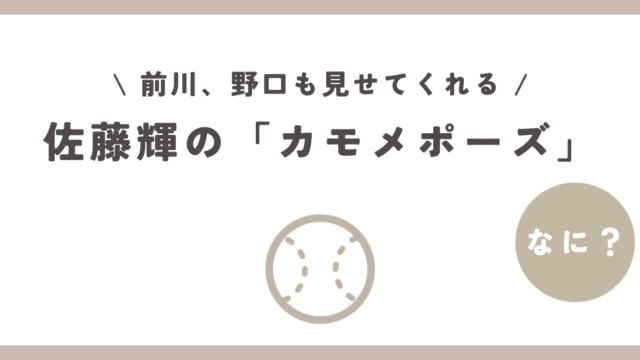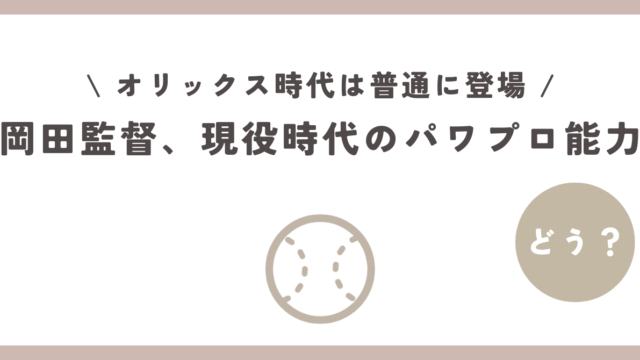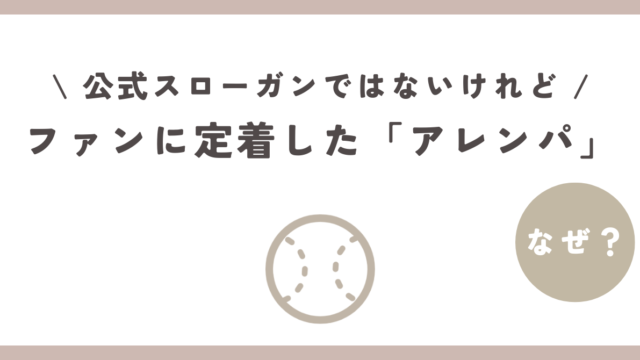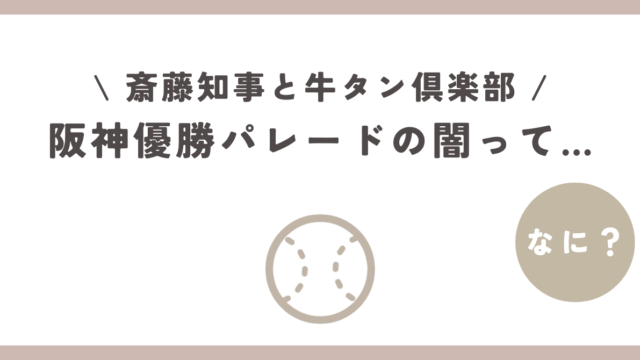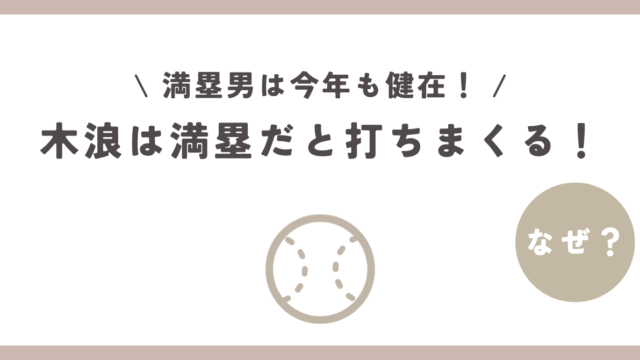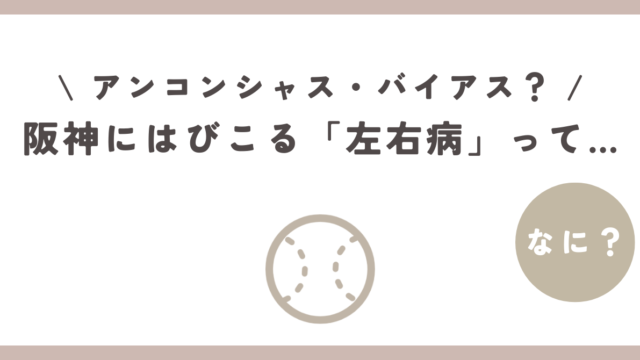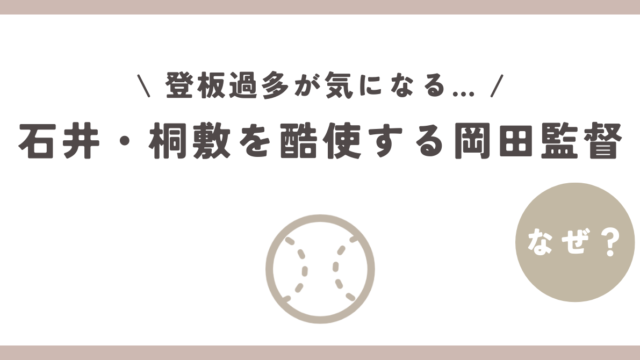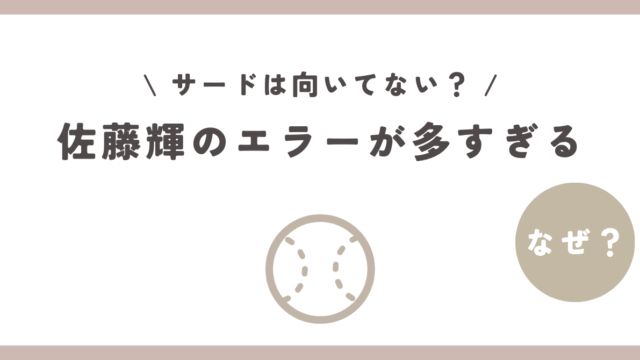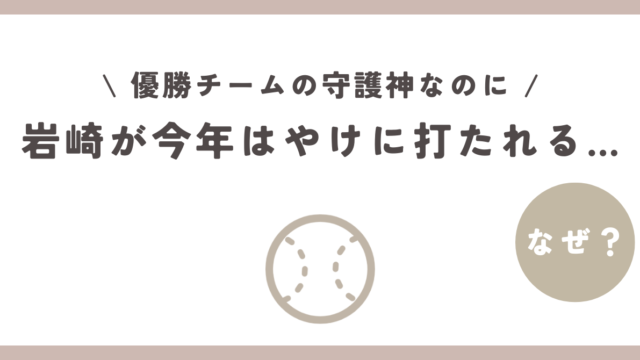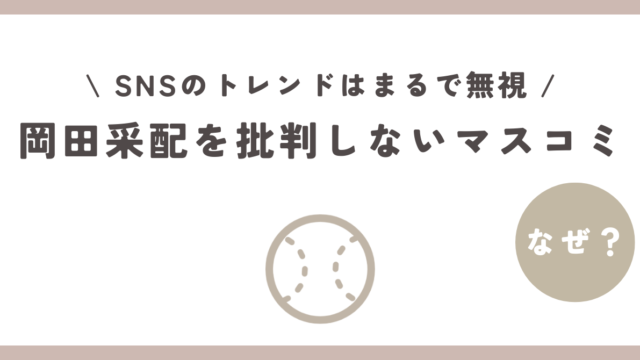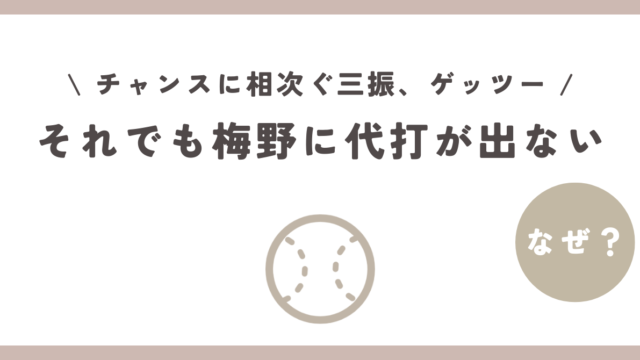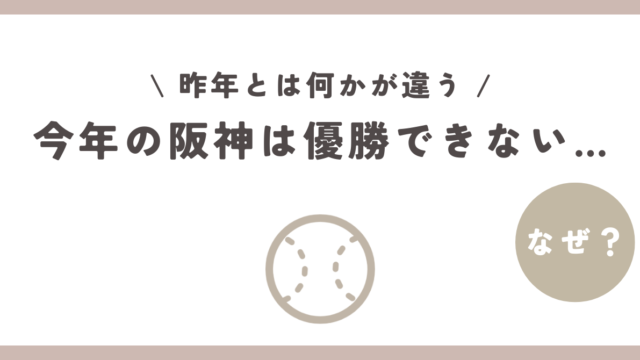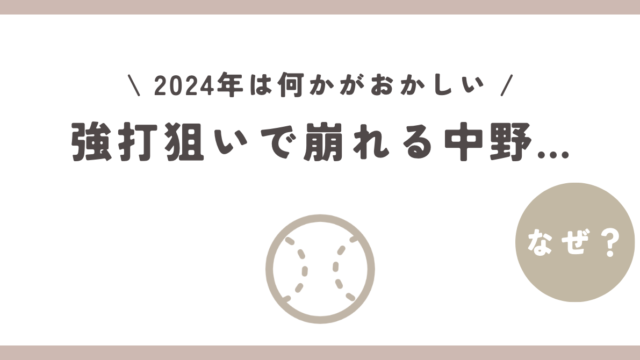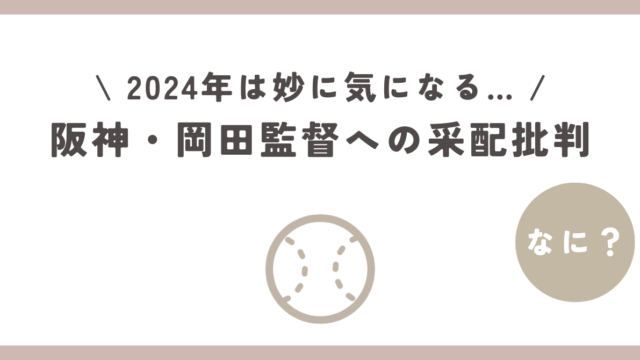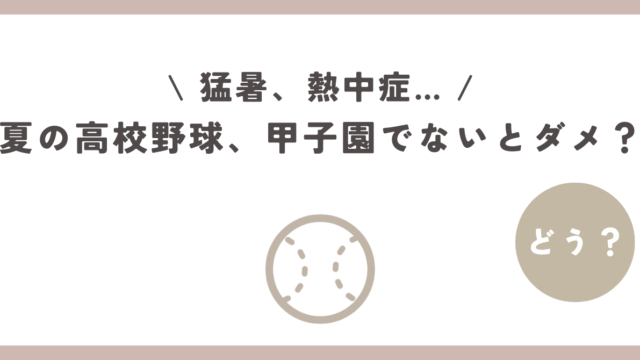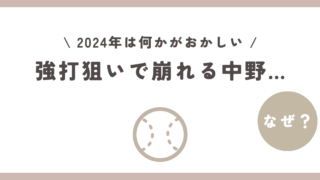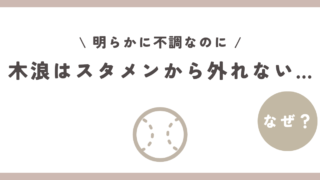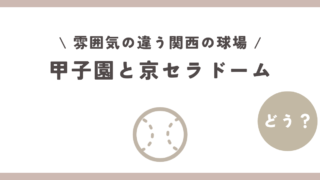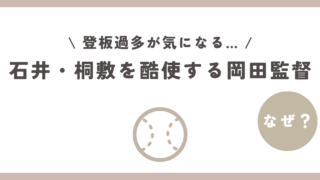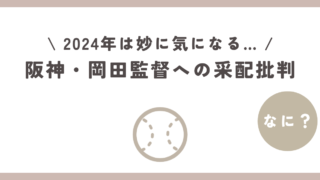高校野球の延長は何回まで?タイブレークとは?ルールを解説!

高校野球では、延長戦やタイブレーク制度が試合の展開に大きな影響を与えています。延長は何回まで行われるのか、タイブレークとはどんな仕組みなのか。
本記事では、そのルールや導入理由を詳しく解説します。最新のルールを知ることで、高校野球の新たな魅力に気づき、観戦がさらに楽しめるようになります。さらに、タイブレークが生んだ名勝負もご紹介します。
高校野球のタイブレークとは?仕組みを簡単解説
高校野球のタイブレークって最初は反対意見多かったけど、なんだかんだで面白いルールだなと思う。
今日の大社と早実なんてタイブレークがあったから盛り上がってる部分もある。
名勝負だった!
pic.twitter.com/RbGRgcmxjr— ネム@競馬とジャグラー大好きギャンブラー (@YLMBY26Z6m3EZPf) August 17, 2024
高校野球では、試合が9回で決着しない場合に延長戦が行われます。延長は最大15回までとされ、全国大会ではその後に再試合で勝敗を決める仕組みです。一方、地方大会では都道府県ごとの規定により、抽選で勝敗を決める場合もあります。
選手の健康を守りつつ試合を効率化するため、2018年からタイブレーク方式が導入されました。このルールは2023年に改定され、延長10回から適用されるようになっています。無死一・二塁の状況から始まるタイブレークは、試合時間を短縮しつつ、選手の体力負担を軽減する仕組みです。
観戦をより楽しむために、日本高等学校野球連盟(高野連)の公式サイトや各都道府県高野連の案内を確認することをおすすめします。最新ルールを把握すれば、試合の見方がより深まり、感動が増すことでしょう。
高校野球タイブレークの導入理由とは?
タイブレークは、延長戦をスピーディーに進め、選手の健康を守るために設けられた特別ルールです。2023年からは延長10回以降に適用され、無死一・二塁の状態で攻撃がスタートします。
導入の背景には、1人の投手が連投を強いられることで肩や肘に大きな負担がかかる問題がありました。また、長時間に及ぶ試合は大会運営にも影響を与えるため、改善が急務とされていたのです。
タイブレークの仕組みでは、前イニングの続きの打順で攻撃が始まり、一塁と二塁には特定の打者がランナーとして配置されます。この状況が得点を生みやすくし、試合の決着を早めます。
こちらでは、具体的な戦略への影響を詳しく解説します。
タイブレークが試合展開に与える影響とは?
タイブレークの導入は、高校野球に新たな戦略性をもたらしました。攻撃側は無死一・二塁からスタートし、送りバントで走者を進めるか、強攻で得点を狙うかという判断が求められます。これにより、監督や選手の瞬時の判断力が試される場面が増えています。
守備側も、バント処理や併殺プレーの精度が試合の流れを左右します。内野守備の配置や投手の配球は、これまで以上に緻密な戦略が必要です。
タイブレークのルールは、試合をスピーディーに進行させるだけでなく、短期決戦の緊張感を生む効果もあります。実際に、2017年甲子園では無死一・二塁からの得点率が約70%に達し、攻撃戦略が試合展開に大きな影響を与えたことが示されています。
タイブレークが生んだ高校野球の名勝負
タイブレークは高校野球に数々の名勝負を生み出してきました。2018年の第100回大会では、金足農業が横浜との延長13回タイブレークを制し、エース吉田輝星の活躍で劇的なサヨナラ勝ちを収めました。この試合は観客に深い感動を与え、伝説となりました。
2021年の選抜準決勝では、東海大相模が明豊を延長10回タイブレークで逆転サヨナラ勝利。終盤の緊迫感ある攻防が大会を象徴する名シーンとなりました。さらに、2022年の選抜では、大阪桐蔭が東洋大姫路を破り、タイブレークの緊張感を存分に発揮した試合が展開されました。
これらの試合は、タイブレークが高校野球に新たな戦術とドラマをもたらしていることを示しています。
まとめ
高校野球の延長は何回までなのかについて紹介しました。高校野球における延長戦はタイブレーク制度の導入により大きく進化しました。このルールは、延長10回から適用され、選手の健康を守りつつ試合をスピーディーに進行させる役割を果たしています。
これまでの名試合では、選手の技術や判断力が試され、観戦者に緊張感と興奮を提供しました。例えば、2018年の金足農業対横浜戦や、2021年の東海大相模対明豊戦では、劇的なサヨナラ勝利が生まれました。
タイブレークは高校野球をさらに魅力的にする要素です。次の大会でも、新たな名勝負が誕生することを期待し、ぜひその瞬間を目撃してください。
関連記事:PL教団の有名人は誰?やばいと言われる理由とは?信仰や教えも調査!