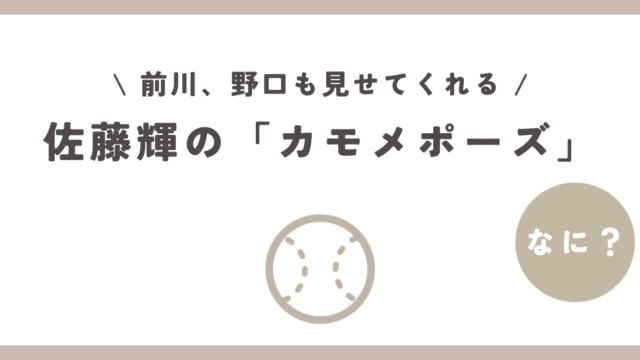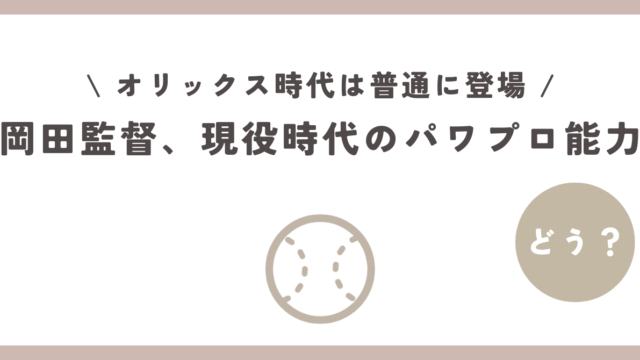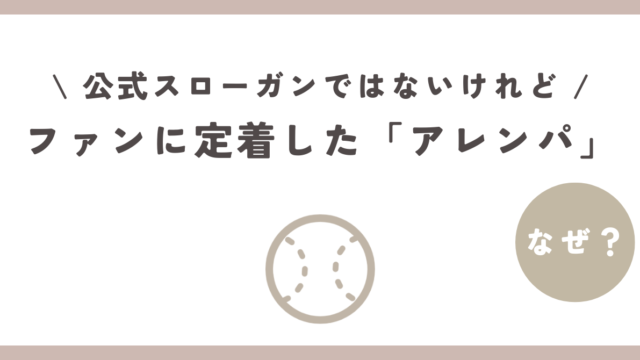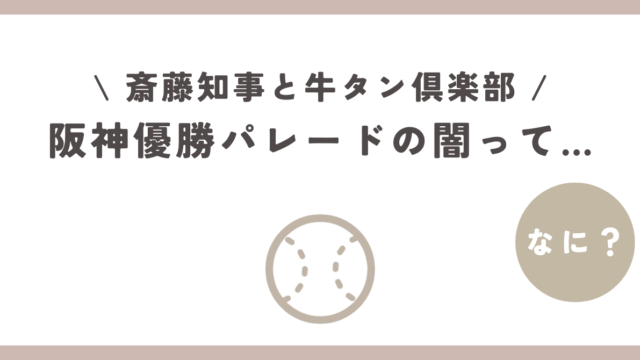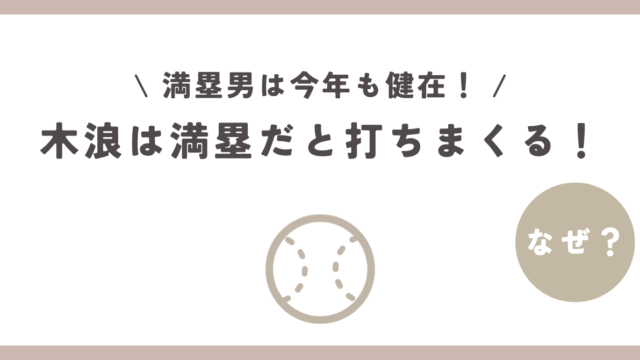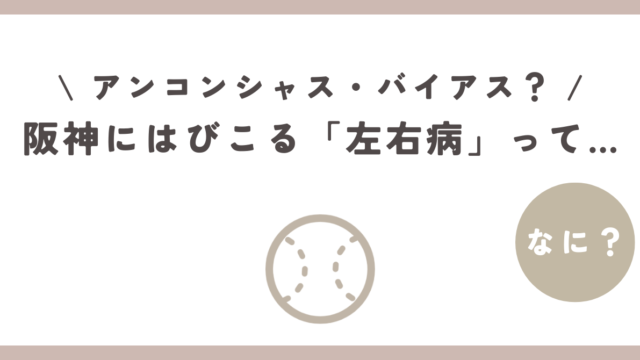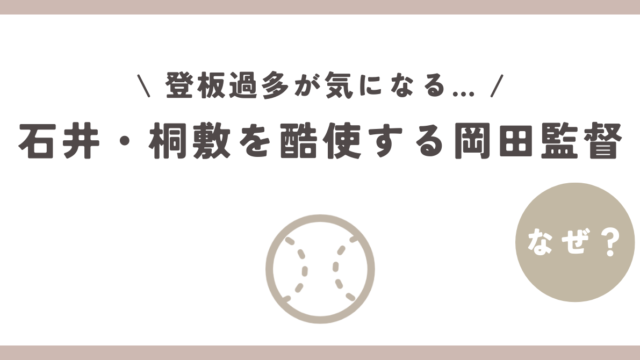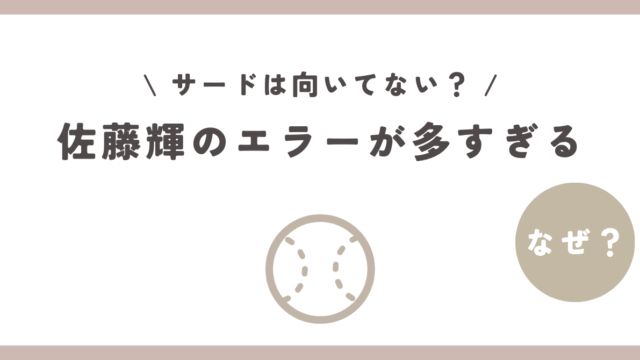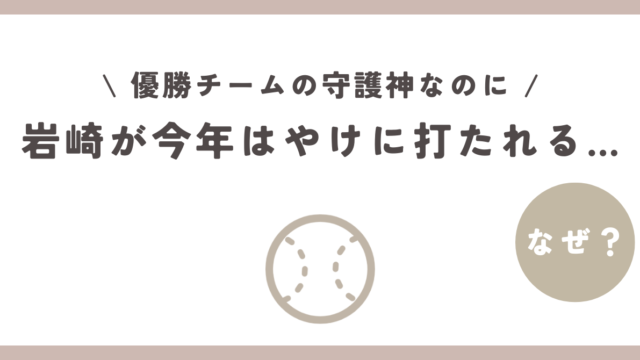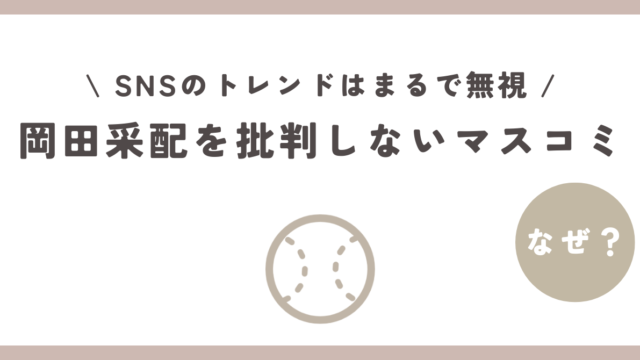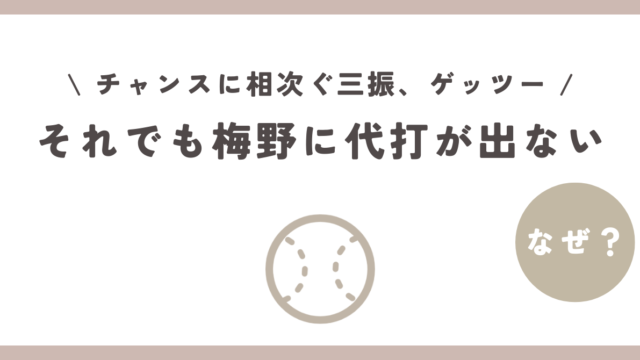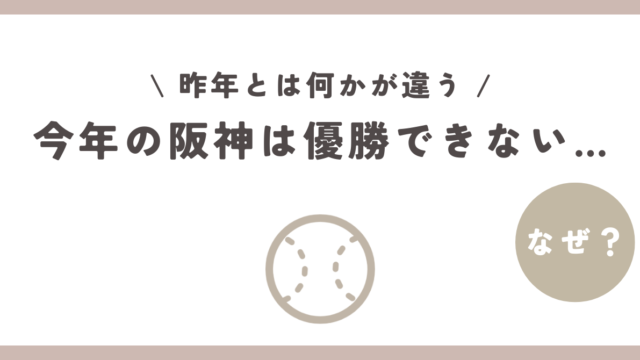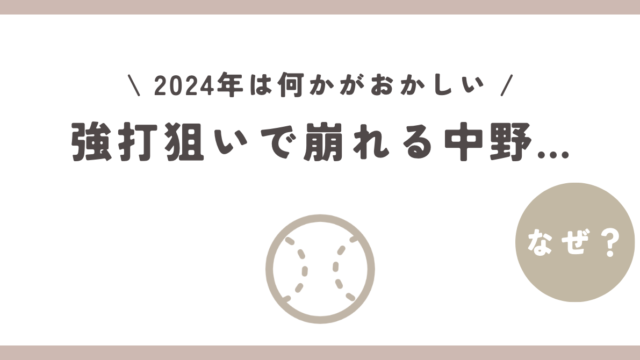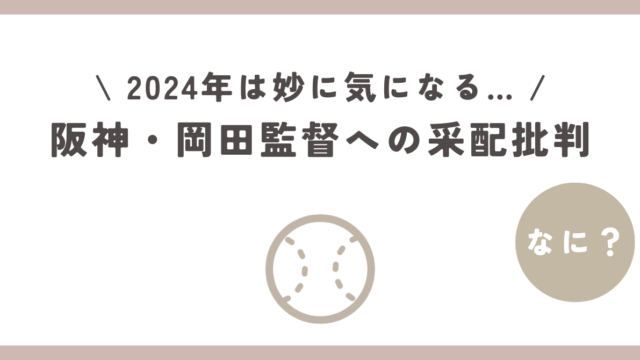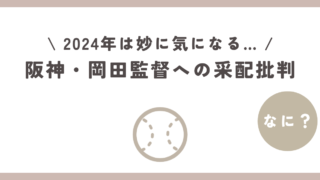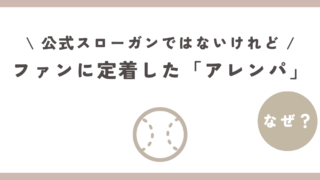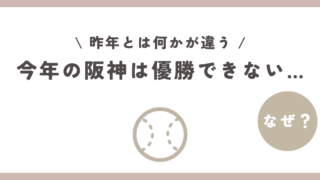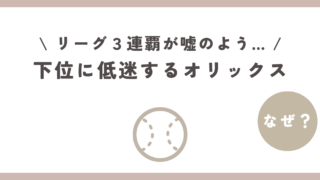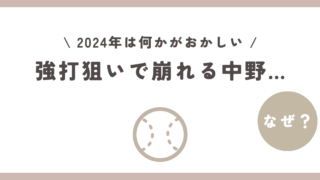トルネード投法の有名な投手は誰?禁止になる可能性も?ルールも確認!
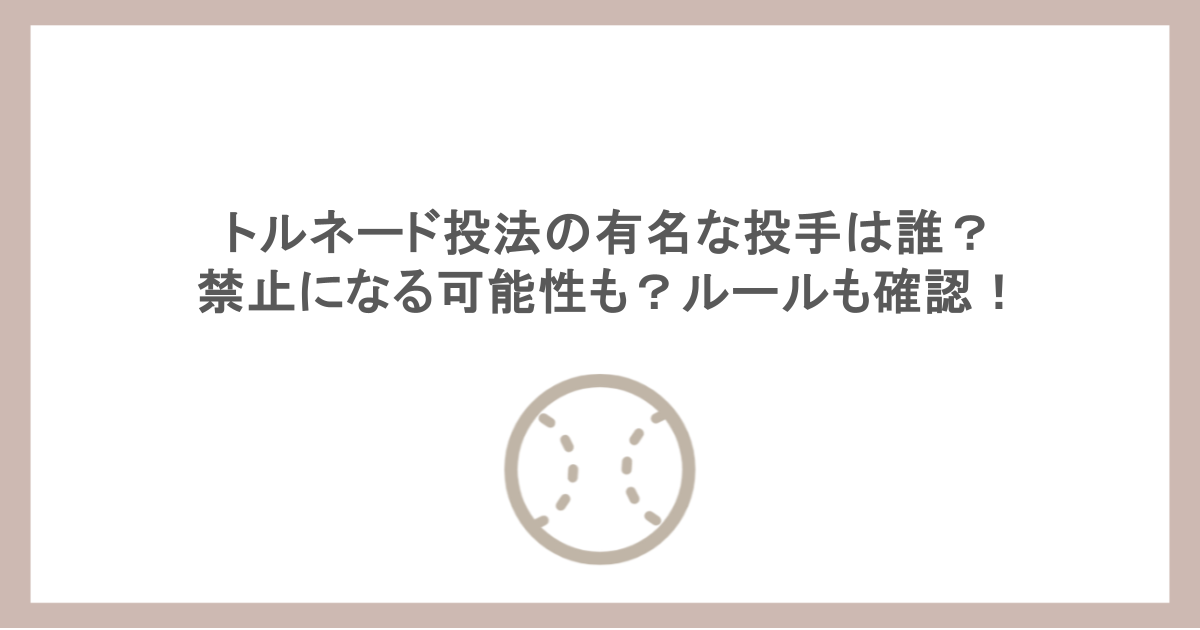
大きく体をひねって背中を打者に向ける”あの投げ方”が気になった人は多いはずです。トルネード投法を使う投手として知られる野茂英雄やティアントの映像を見ると、回転の深さが球威や打者の反応に与える影響の大きさがよく分かります。ルール面の誤解や禁止説も混ざりやすいため、特徴・有名選手・ルール上の使用可否をまとめて整理しました。
本記事では、トルネード投法の魅力と注意点をわかりやすく解説します。
トルネード投法とは?
トルネード投法を使う投手の動きは、深いひねりと大きな回転を組み合わせて強い推進力を生み出す独特の構造が特徴です。一般的なワインドアップより回転角度が大きく、上体を打者と正反対へ向けるため出どころを隠しやすい点も見逃せません。
下半身の沈み込みと上半身の遅れが連動し、球威が増す一方で体軸の維持には高いバランス能力が求められます。こうした長所と課題を併せ持つ、変化の大きい投げ方です。
トルネード投法の投手が打者を欺く理由
腕を高く上げて上体を深くひねり、ためたねじれを瞬時に戻すことで強い前方への力を作ります。投球途中に上体が打者と正反対を向く動きが入るため、リリース直前まで腕が視界に入らず、打者の判断が一瞬遅れやすくなります。
長いモーションから急激な回転へ移る流れにより、空振りや芯を外す打球を誘いやすいのも利点です。反面、回転量の大きさがリリース位置のぶれにつながり、制球の難しさが残る点も見逃せません。
参考サイト:full-Count
トルネード投法の代表的な投手は誰?
派手な回転で観客の視線を集めてきたこの投げ方には、歴史を彩る象徴的なピッチャーがいます。トルネード投法を使う投手として日本とMLBの両方に名を残した選手たちは、成績だけでなくフォームそのものでも強い印象を残しました。
こちらでは、その代表格と、現代のアレンジ型フォームの傾向を紹介します。
野茂英雄
日本でトルネードといえば、まず野茂英雄の名前が挙がります。近鉄時代の1年目から新人王・最多勝など複数のタイトルを獲得し、一躍リーグを代表する投手となりました。1995年にMLBへ挑戦してからも新人王と奪三振王を獲得し、渦を巻くようなフォームは「トルネード」の名で世界に広まりました。
映像では、足を高く上げて深く体をひねり、上体全体を打者側と正反対へ向ける動きが際立ちます。この大きな回転と力強い上半身の戻りが球威につながり、打者の反応をわずかに遅らせる要因になっていました。
出典:SPOTVNOW
ティアント
メジャーの歴史でこのタイプの原点といわれるのが、レッドソックスなどで活躍したルイス・ティアントです。投球前に上体を深くひねり、ボールではなく背番号だけが打者の視界に入るような姿勢を作るフォームで知られました。この極端な回転は、リリース位置を見えにくくすると同時に、独特の間合いとリズムを生み出します。
野茂のフォームにも似た部分があり、キューバ出身で「トルネード」と呼ばれることもあり、今でもメジャー史に残る個性的な投げ方として語られています。
現代のトルネード投法を使う投手はミニ型
最近は、往年のように完全なトルネードを採用する投手は多くありませんが、動きの一部を取り入れた「ミニ・トルネード」はむしろ増えています。上半身のひねりだけを少し大きくしたり、ステップ幅を広げて推進力を高めたりと、自分の体格や柔軟性に合わせて変化をつける例が目立ちます。
SNSや動画サイトには、そうしたアレンジを試す学生やアマチュア投手の動画が数多く投稿され、プロの変則フォームと比較する解説も増えています。このように、完全コピーではなく「要素取り」の形で現代野球に生き続けている投げ方です。
トルネード投法はルール違反?
豪快な回転を見ると、「本当にルール上問題ないのか」と不安になる人もいるでしょう。トルネード投法を使う投手の映像だけを見ると派手に映るため、SNSでは過剰に危険視される場面もあります。
こちらでは、公認野球規則との関係や、ボークとの線引き、そして「禁止説」が生まれた背景を整理します。
公認野球規則はフォーム自体を禁止していない
このフォームそのものが公認野球規則で一括して禁止されているわけではありません。MLBやNPBのルールが定めているのは、ワインドアップかセットかといった姿勢、プレートの踏み方、そして投球動作へ入る順番などの手順が中心となっています。
上体をどこまで回してよいかといった角度までは条文に明記されておらず、正しくプレートに触れ、途中で止まらず一連の動きで投げていれば、トルネード型のフォームも原則認められる整理です。
軸足のずれや二段動作はボークになる場合がある
フォームそのものではなく動作の「切れ目」に注意が必要です。回転が大きい投げ方では、軸足がプレートから離れてしまったり、途中で静止したように見えて二段動作と判断されると、ボークとみなされる場合があります。
特に走者がいる場面でこのフォームを使うときは、始動からリリースまで途切れなく流れるように投げ切る意識が重要です。事前に動画で自分の動きを撮影し、第三者の目線で不自然な間やプレートからの離れ方がないか確認しておくと安心できます。
禁止説が広まった背景にある誤解
「派手なフォームは危険だからそのうち禁止される」といった話がSNSで広まることがありますが、現時点で投げ方そのものを禁止した例は見当たりません。実際には、話題になった二段動作の判定や、途中静止をめぐるボークの議論が元になっているものが多く、フォームの問題と混同されているのが実情です。
こうした投稿の多くは具体的な条文や審判の見解に基づいておらず、印象だけが独り歩きしがちです。噂に振り回されず、公式ルールや競技団体の説明を確認する姿勢が大切だといえます。
まとめ
トルネード投法は深いひねりから連続した動きで投げ込む独特のフォームで、代表的なトルネード投法を使う投手には野茂英雄やルイス・ティアントがいます。フォーム自体は公認野球規則で禁止されておらず、問題となるのは軸足の移動や途中静止などボークに関わる動きだけです。
強い回転で球威が増し、リリース位置を読まれにくい利点がある一方で、制球の難しさや腰・肩への負担も避けられません。興味がある人は体力に合わせて少しずつ取り入れ、指導者と相談しながら安全な形を模索してみてください。